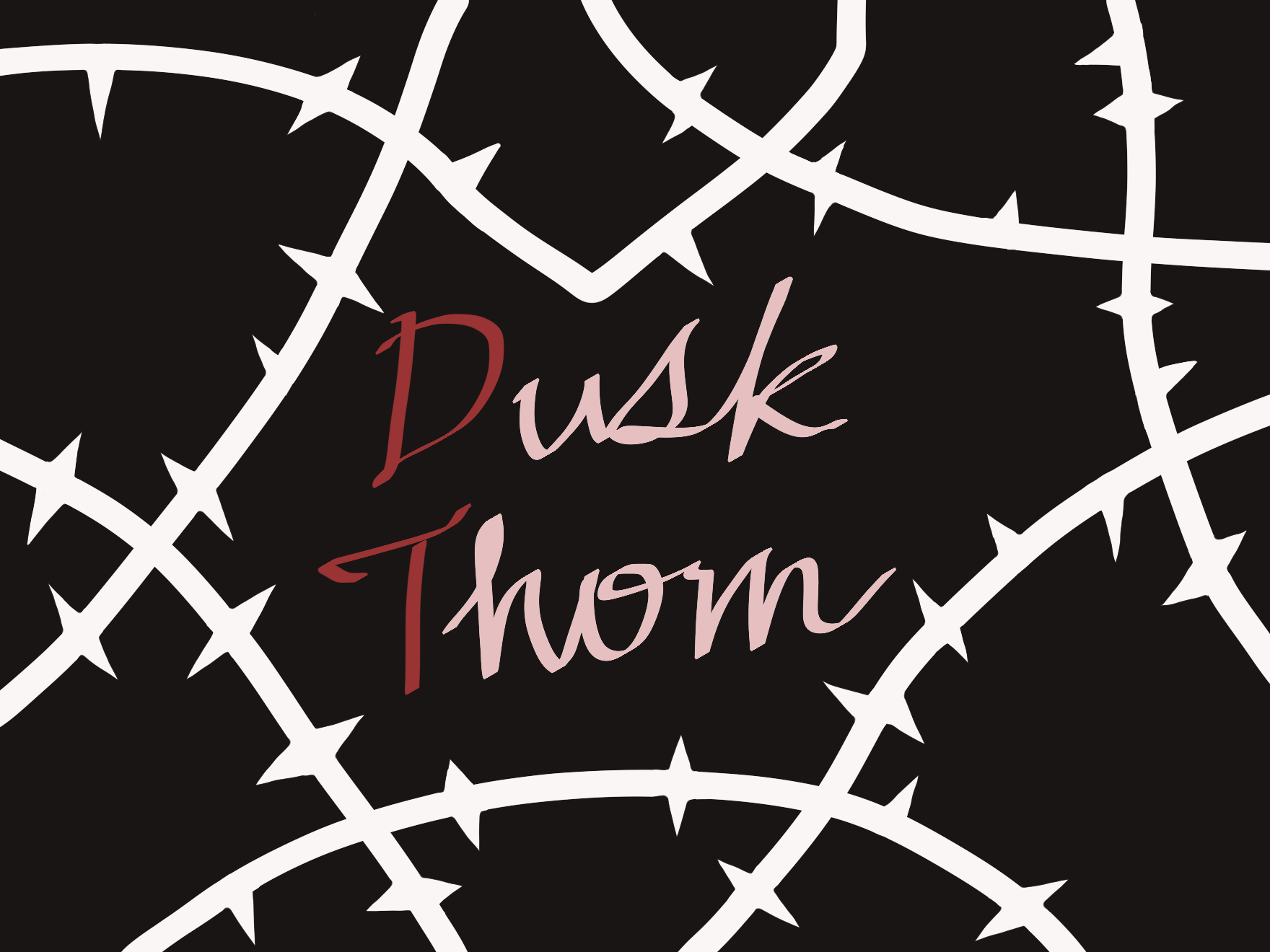別れたはずの過去との縁
「仇って……どういうことですか?」
いきなり父親の仇なんて言われても、どういうことか分からないんだけど。
「マキちゃんの両親が遭った事故は転落……確か二人が乗った車両が崖下で破損していた状態で発見されたんだったね。ブレーキ痕はあったから事故当時は心神喪失状態ではないと言われていたけど……車は相当な衝撃を加えられていて、発見現場の崖から落ちたには状態が酷すぎるって話だったな……そこに事件性があるってことか?」
伯父さんがフォローしてくれた。偶然の事故じゃなくて、誰かが殺そうとした。でもどうして急に3年前の話が?
「はい。セルペンテの襲撃犯から聞けたのは、『桃瀬という名字を持つ中国籍の女性を、ボスが探している』『ボスはその人が持つ土地の権利を欲している』『そこの土地は元の所有者が死んだときにボスが手に入れるはずだった』ということです」
「桃瀬……アタシの名前」
「私はこの名字を持っている人に心当たりがありました。マキさんともう一人、この免許証の持ち主です」
「お父さんと知り合いだったんですか!?」
「私は知り合いではありません。私が一方的に名前を知っていただけです」
「じゃあなんでお前がこの名前を知っているんだ?」
「彼、地主だったんですよ。衆合街の北東部全域の」
青天のへきれき? というか今明かされる衝撃の真実。お父さんがここの土地を持っていたなんて。
「北東部は中国人が多く住まう雑居ビルが乱立しています。衆合街の中でも開発が進んでいないので、狙い目だと思われたのでしょう」
「それじゃあ、マキさんのご両親を殺した犯人は土地の権利を狙って事故を起こした、と……」
「話を聞く限り、そうでしょうね。ターゲットに娘がいて、遺産は既に全て娘に渡されていたのは想定外のようですが」
「お前がそこまで確信を持っている、ってことは相手が誰なのかも解っているんだな?」
「はい。セルペンテの襲撃犯の正体はとある海外組織……の中でも日本に勢力を広げようとしている、ベルゼブブの一派です」
ベルゼブブ、という単語には覚えがある。たしか、セルペンテで黒服の人達の会話にあった。
「ベルゼブブか。……本名じゃあないだろうが、悪魔の名前を名乗っている以上、ロクでもない奴だってことは分かるな。それこそ目の前にいる暗黒闇鬼神よりは」
「私は鬼ではありませんが」
ケンカの気配を察知してしまった。
「えっと、そのベルゼブブっていう人が私のお父さんとお母さんを殺して、お父さんが持っていた土地を奪おうとしたけど、既に私が遺産を全て貰っていたから、ベルゼブブは土地が手に入らなくて、だから私を殺そうとして探している、ってことですか?」
「はい、概ね間違いありません」
今まで言われたことをまとめてみたけど、筋が通っているようでまだ分からないこともある。というか、私がお父さんの土地を貰っていたことについても知らなかった。
「私としては伯父である貴方が、マキさんの相続について関与していないことが驚きです。貴方保護者なんでしょう」
「いやあ、それはね、色々と。僕は妹の財産しか知らなかったし」
「……このことを追求しても今は仕方がありません。この話は後ほどに。このままでは、マキさんがベルゼブブの一派に捕まるまで衆合街のキャバレーやクラブで襲撃が起こり続けるでしょう。マキさんが捕まってしまえば、最悪の事態が起こってしまいます」
「それで、アンタはどうするつもりなんだ?」
白澤さんが机に乗り上げるようにして訊いた。
「決まっています。明々白々、単純明快、潰します」
すごく分かりやすい。
「彼らの本拠地ですが、今、舎弟に探させています。決行は発見次第になってしまいますが……」
「それだったら恐らく黒縄の埠頭だろ。あそこは外国の船も停泊するから外人がうろついていても気づかれにくい。最近、黒い服の奴が増えているって話も聞くしな」
「……そこは盲点でした。よく知っていましたね?」
「まあ、僕は神獣白澤だからね」
「シンジューハクタク?」
初めて聞いた言葉だったから、なんの事か分からなかった。白澤さんは私を見てちょっとびっくりしたような顔をしていた。桃太郎さんが疑問に答えてくれた。
「神様の獣と書いて神獣、中国の吉兆の印と言われているやつだよ」
「……ともかく、この後、埠頭を調べてみます。それから、ベルゼブブ一派への襲撃ですが」
「俺は反対だぞ、そんな危ないところにマキちゃんを連れていけない。だいいち、それじゃあヤクザどうしの抗争じゃないか。マキちゃんが行く必要なんてない、行ってはいけない」
「マキさんはどう思いますか?」
「私、やります!」
「マキちゃん……」
白澤さんは口から零れるように言った。
「それは許可できない。こいつの考えに乗るってことは、こいつらに借りを作るってことだ。ヤクザっていうのは一度縁を結んでしまえばずっと関係が続くんだぞ。僕の妹の仇をとったからって、ありがとうございました、ではさようなら、ってはいかないんだ。ずっと借りを作らされて、用済みになったら捨てられる。そんな奴らなんだよ」
「よく本人を目の前にして言えますね……」
桃太郎さんが、あきれたようにつっこむ。確かに悪口のオンパレードを加々知さまの目の前で言えるのは相当な度胸が要ると思う。
「僕はいいんだよ。既にお世話になってるし。でもマキちゃんは違う。彼女はまだ未来のある女性だ。この一件で彼女の行き先を決めてほしくない。お前みたいなやつに彼女の未来を捨てられたくないんだ」
「それなら、こう言えばいいんですか? 『あなたの姪を私にください』」
「なっ!?」
なんだってえ!?
「私はマキさん……真黍さんに好意を持っています。借りを作らせようとしているのは間違いではありませんが、捨てるなんてあり得ません。むしろずっとそばにいてほしいのです」
ラブコールだった。白澤さんも桃太郎さんも呆然としている。まさかここでそんな話が出るなんて思わなかったし、さんが私のことが好きだなんてまったく分からなかった。ずっとからかわれてたし、恋愛感情なんてこれっぽちも感じられなかったんだもの。
「加々知さんがマキちゃんが好きなのは分かりやすかったけど……」
桃太郎さんから心を読まれてしまった。それじゃ私が鈍感みたいじゃない。いやかなり鈍感だったな。
「と、というか、借りを作らせるって言ったな!そんなこと言われたら、こっちは止めざるを得ないだろ!」
「あなたがそう言わせるように誘導したんでしょう。責任をとるのはあなたのほうです」
「聞いたことないぞそんな理屈!」
「あの……」
このままじゃいつまでたっても話が進まない。私が気持ちを伝えないと。
自ら危険に飛び込むなという伯父さんの言うことは最もなんだけど、私は私で、考えている。この街に来てから、初めて私は伯父さんがいたこと、お父さんが私にくれた遺産のことを知った。学校で居場所のなかった私に、生きる意味をくれたのはこの街だった。お父さんから貰ったものを守りたいし、加々知さんに対する恩もある。加々知さんはさっき、私に借りを作らせるって言ってたけど、私にとってはすでに借りがある。
「私がこの街を守ることができるなら、やりたいんです。私がこの街に恩返しをしたいんです。私は何をすればいいんですか?」
「マキさんに荒事はさせませんよ。まずはこの人に連絡してください」
そういって加々知さんは懐から紙切れを取り出して私に渡した。受け取るとそれは名刺のようだった。白澤さんと桃太郎さんが私の後ろに回って名刺を覗き込んだ。
二人と彼らの街
作戦会議の次の日、私は加々知さんに渡された名刺の人物に会いに待ち合わせ場所の喫茶店にいた。
「……刑事部捜査第四課、警部補の……」
「はい。源義経です。貴女が桃瀬真黍さんですね。本日は貴女一人ですか」
「加々知さんは別の用事があるとのことなので、来ていません」
源義経、と名乗った男性は、纏っているオーラが大物芸能人みたいだけど、見た目は華奢な少年そのものだった。警察っていえば屈強な人たちばっかりだと思っていたし、なにより加々知さんの知り合いというならさぞムキムキな人だろうと想像していた。私は義経さん(ホントは源さんと呼ばなきゃいけないんだろうけど義経さんと呼びたくなる)テーブルの向かいに座った。すぐに来たウェイトレスにアイスティーを注文した。ウェイトレスがテーブルから去ってから、溜め息をついた。
「えぇっと……加々知さんとはどういう関係なんですか?」
「本人から聞いていませんか?……加々知輝さんとは、まあ腐れ縁みたいなものですよ」
義経さんは声を小さくして話を続けた。
「彼が私を頼るなんて滅多にないことですし、貴女のような代理人を立てることは今までに一度もありませんでした。彼は今よっぽどの問題を抱えてるんですか?」
私は加々知さんに言われた通りに説明をした。海外マフィアに命を狙われていることは伏せて、アルバイト先のクラブで拐われかけたことを話した。
「その、貴女を拐おうとした人はどんな人物像か思い出せますか?」
「えぇっと……確か黒い服を着てました。あと英語?を喋ってて……ベルゼブブがどうとか言ってました」
「ベルゼブブ……」
義経さんは何か考えているみたいだった。
「その話……他に何かありますよね?……まァその辺りはあの人自身で片付けるつもりなんでしょうけど……とりあえず、この話はこれで持ち帰りますね。またお話を聞かせてもらいますので、連絡先を教えてください」
「あ、はい」
義経さんが懐から取り出したメモ帳に私の住所と電話番号を書いた。メモ帳を返すと、義経さんは私に聞いた。
「この後はどうするんですか?」
「あー……加々知さん……オーナーさんのキャバレーがまだ襲撃されてないので、そこにお世話になろうかと思ってます」
「送りましょうか?」
「同伴なら喜んでお願いします」
「仕事中ですので同伴は無理ですね」
「だめかー」
とは言いながらも、義経さんはキャバレーの従業員入口まで送ってくれた。別れ際に、絶対に一人で無理はしないように、と真剣な眼差しで見つめられながら言われた。うーん、顔が良すぎる。
久しぶりに訪れたキャバレーのバックヤードに訪れると、何人かの女の子が準備中だった。その中の一人が私に気づいて駆け寄ってくる。
「マキちゃん!生きてた!」
「死んでないよ!?」
ミキちゃんは相変わらずのようだった。どうやら私がセルペンテに移動したあと、キャストの間で、色々噂になってしまったらしい。いや、まさに命の危機ではあるんだけど。
「オーナーさんからの指示で、しばらくはまたここで働くことになったんだ」
「じゃあ、また一緒にいられるってことだね!よかったぁ……」
よかった、という声が、ミキちゃんをいままでどれだけ心配させてしまったのかがわかった。……そういえば、ミキちゃんが私以外のキャストの女の子と一緒にいるの、ほとんど見たことない気がする。
1週間も経っていないのに、とても懐かしい気持ちになる。たった1週間で、自分を取り巻くあらゆるものが大きく変わってしまった。きっと、あのベルゼブブっていう人をやっつけたところで、私はまたこうやっていままでと同じ生活はきっとできないだろう。そう考えると、なんだか寂しくなった。
常連さんから、動作が大人っぽくなったね、と褒められたり、急にいなくなった私を心配してくれたりしてくれて、ここだけは変わっていなくて、私だけが変わってしまったんだ、と実感した。日付が変わろうとするとき、最後のゲストを見送ってから、さあ片付けのお手伝いでもしようかな、とホールに向かったところで、急にエントランスが騒がしくなった。
心臓がどきどきする。セルペンテでの出来事を思い出した。あのときのような、何の話をしているのかわからない言葉が飛び交っているのが聞こえる。物陰に隠れてエントランスのほうを見ると、黒服の男たちがボーイさんたちの静止も聞かずに入り込んでいた。
私は、急いでバックヤードに戻って、電話機を取った。震える指で慎重に番号を押していく。コール音は1コールで終わった。
「はい」
聞き慣れた声。地獄の底のように低くて、それでも優しい声。
「加々知さん、あの……!」
「わかりました、今すぐ突入します」
電話が切れるのと同時に、もしかしたら切れるより早かったかもしれない。急に足音の数が増えて、ホールが騒がしくなった。誰かの叫び声と、ものがぶつかりあう音が聞こえてきた。ホールに繋がるバックヤードのドアを開けたら、ホールから逃げてきた女の子達がなだれこむように入ってきた。
「ヤバイ、ヤバイってあれ!」
「怖すぎ、なにあれ。っていうか誰?あの人たち」
口々に言い合う避難者を見た、もう帰り支度を済ませているミキちゃんが私に話しかけた。
「……何が起こってるの?」
私は戸惑いながら答えた。
「団体客……みたいな?」
それから数週間。私はセルペンテでのアルバイトを再開した。キャバレーについては、つい昨日、営業を再開したことを唐瓜くん達から聞いた。キャストのみんなは全員、無事だったみたい。
「兄貴から言伝を貰ってます。『来てほしいところがあるので、今日か明日、時間に余裕があるときに会いたい』と」
「ずいぶん急だね」
「急ぎの用であることは聞いてます。兄貴もなるべく早く済ませてセルペンテに行きたいと言ってましたし」
「どういう内容なのかは知っているの?」
「いや、詳しくは……一連の襲撃事件に関する話です、確か」
「それなら確かに早いほうがいいね、お香さんに今日は早めにあがれるか聞いてみる」
「えっ、そんな急に大丈夫なの?心の準備とか必要じゃない?」
茄子くんが心配そうに尋ねた。
「心の準備って言ってもどんな準備をすればいいかわかんないし……とにかく連絡取ればいいんだよね」
「……マキさんすげぇなあ」
「うん?どこがすごいの?」
「そういうところ」
すごく濁された気がする。
今日早くあがれることをお香さんから聞いた後、私は加々知さんに電話をかけた。今日でもいいと言われたので、迎えに来てもらうことにした。
帰り支度をして、待ち合わせ場所に向かうと、そこには黒塗りの車の隣に加々知さんがいた。加々知さんは私に気づくと、だまって後部座席のドアを開ける。
「えっと、どこへ向かうんですか」
「それほど遠くない場所ですよ、危険なところではありますが、安全は保証します」
どっちなんだ、それ。
私はされるがまま後部座席に座ると、加々知さんは運転席に乗った。
車の窓はサングラスのように黒く、夜だと全く外が見えない。時々停車するから、信号のある場所――人通りのある場所なのはわかった。
最初の数分間は、車のモーター音だけが響いていた。そのうち、加々知さんが口を開いた。
「襲撃事件の犯人である、ベルゼブブの一派は、キャバレーで暴れた後、暴行罪で現行犯逮捕されました。また、彼らの根城であった埠頭の倉庫は、既に警察により介入されています。ベルゼブブの日本での活動は、実質潰えたと言っていいでしょう」
「ベルゼブブさんは、逮捕されたんでしょうか」
「彼だけは警察の手から逃れてしまったようです。また、力をつけて戻ってくることはあるでしょうが、しばらくは無理でしょうね」
それから、着きましたよ、と加々知さんが車から降り、後部座席のドアを開けてくれた。
どこかの駐車場らしい。私は加々知さんに連れられて、雑居ビルの中に入った。階段を降り、金属製の扉に着く。加々知さんは慣れた手付きで鍵を開け、扉を開いた。中は真っ暗だった。
「どうぞ」
どうぞと言われても。
加々知さんは扉をくぐり、部屋の照明を付ける。部屋の中央には一人の男性が力なくうなだれて座っていた。
「彼がベルゼブブです。マキさんのご両親の殺しを計画し、マキさんを殺そうとした人物です」
ベルゼブブ、と呼ばれた男性は私の顔を見て「お前が桃瀬真黍か」と掠れた声で呟いた。日本語は通じるらしい。私を見つめる目は怒っているかと思ったけれど、諦めているみたいだった。
「彼の生殺与奪の権利をあなたに与えます。猿轡はしていませんが、手足は縛られていますからマキさんに危害は加えられないはずです」
「ベルゼブブを殺せば両親は帰ってきますか」
「帰ってきません。ただし殺せばこれ以上彼はマキさんを殺しに来たりはしません……マキさんに殺しはさせたくないのですが」
さっき生殺与奪の権利を与えるって言ってたのに。加々知さんも私の気持ちに対して葛藤があるみたいだった。
「えっと……ベルゼブブさん。私の両親を殺して、もし土地が手に入ったら、どうするつもりだったんですか」
「……そんなことを聞いてどうする。お前の望む答えが聞けるはずないだろう」
「わかってます。……わかってはいるんですけど、ここで命乞いをするなら殺してもらおうかな、って」
自分で自分の言葉が怖くなる。
「でも、ベルゼブブさんは、そういうことしなくて、えっと、ここで殺してくれ、って考えてますよね。ここで死にたがってるっていうか。……だったら、ちゃんと、衆合街から、日本から出て行ってください。それで、もうここに来ないなら、私はそれが一番いいです。加々知さん、それでいいですか」
「わかりました。明日、《出荷》の手続きを開始します。宛先はEUでいいでしょう。」
「EUってヨーロッパの偉い人の集まりですっけ?そんなところにこの人を送っても大丈夫なんですか?」
「隠語みたいなものですよ、偉い人の所には送りません。……お疲れ様でした、マキさん。家まで送りましょう」
「はい、帰りましょう。私達の街へ」