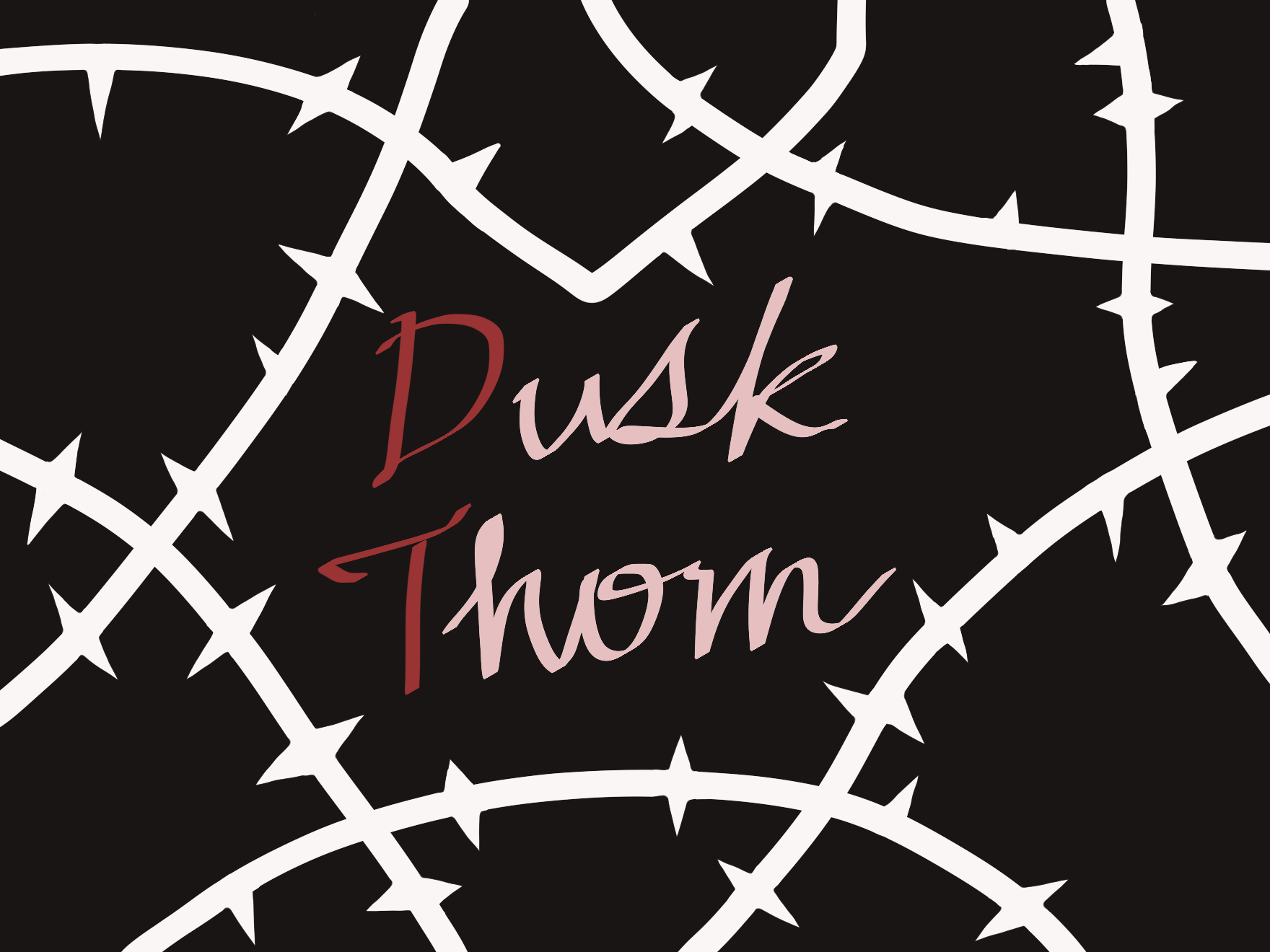裏には裏の事情がある
寄るところがあるとは言ったが、加ヶ知が用のある人は神出鬼没である。いつもであったら、ある裏道のホームレスの溜まり場で薄汚れた男らと酒盛りやら賭け将棋やらで盛り上がっているはずだったが、今日はどうやら”まだ”来ていないらしい。さて、連絡先も持たぬ相手にどうやって連絡を取ろうかと考えあぐねていると、自分の探していた男の声がした。
「加ヶ知のアンちゃん、いつもより眉間に皺をよせてどうしたんか」
「貴方のせいでもありますよ、檎さん。あなたに調べてもらいたいことがあります」
檎と呼ばれた男は虚空な笑みを浮かべながら加ヶ知に近づいた。
「それでさっき公園に来とったんじゃのォ。その話はわしの話を聞いてからにしんさい。……いやァね、ちょいと調べモンをしとったらこんな時間になってしもうたんです。普段の仕事を圧迫するわけにもいかんが、どがァしてんアンちゃんの耳に挟んでほしいことがあるんじゃ」
檎はこの街で幾つかの風俗店経営を任されている。さらに街の至る所に情報網を持ち、衆合街のことでは彼が知らないことはない。かどうかは知らない。
「その”調べもの”の対価は?」
「これはアンちゃんのために集めた情報じゃけぇ、お代は頂かん」
いつもよぉして頂いとるけぇの、と笑いながら檎は懐から煙草を取り出し、火をつけた。
アンちゃん、EUって知っとるか?」
「欧州連合、ヨーロッパの地域経済統合体ですね。それがどうかしたのですか」
「いやいや、それじゃのうて。どうやらそがいな名前の海外マフィアがあるんじゃげ。海外マフィアは極道と違うて自分の所属を明かさんのが普通じゃが、こいつらはよう身分を明かしとるようなんじゃ。恐らくスジモンを挑発するためじゃろう。奴らはどうやら人を探しよるらしい。それが誰だかは結局分からんかったが……。奴らはそろうて黒い服装で固めてキャバレーやらクラブやらを襲うとるらしい。アンちゃん、知っとるか?」
「キャバレーやクラブを襲う……。つい先ほどセルペンテで襲撃があったようですが……襲撃犯はすでに捕まえているので彼らからも話を聞く必要がありますね」
セルペンテに現れた襲撃犯がマフィアに所属しているのであれば今後自分のシマにもちょっかいを出してくるだろう。お香さんやマキさんを別の店に避難させていても危険は及びかねない。政治経済同盟と同じという名前の是非に関しては頭の片隅に一旦置いておく
「奴らの標的は引き続き調べとく。それで、調べてもらいたいことっていうんは何か?」
「マキさん……桃瀬真黍さんのことです」
「ああ、今アンちゃんがお熱な女の子か。スリーサイズとかか?彼女に直接聞きゃあえぇじゃないんか」
「まァそれくらいなら直接聞いたほうが良いでしょう。私が知りたいのは彼女の出生です」
「故郷の話ならいい酒の肴になるじゃろう」
「つくづく察しが悪いですね貴方は。彼女は自分の過去を話したがらない。私はその理由が知りたい」
「ハハァ、成る程。なかなかのサドじゃな」
「貴方とは趣味が合わないと見ました」
「ワシもそう思う」
「頼みましたよ。EUについては私も調べておきます。貴方のオーナーにも細心の注意を払うよう伝えておいてください」
「ああ、よろしゅう。この街にも重要なことになるじゃろうけぇ」
極道が自分の勢力範囲を守るのは単純に自分の力を誇示するためだけではない。表の世界を生きる堅気たちをこれ以上の危険に曝さない。陰で彼らの生活を守るのも役目の一つではある。しかし馬は馬連れ鹿は鹿連れ、同声相和、同気相求む。外からは絶えなく危険が降ってくる。わざわざ自ら危険に身を投じるものもいる。如何に理想が遠いものかは想像に難くない。ヤクザが必要とされている以上、街の治安が向上することはないのだ。
さて、いまやるべきことは優先度降順でマキさんの捜索、マキさんへのプレゼント、最後にEUの動向。プレゼントに関してはマキさんに直接決めてもらいたい。故にマキさんを見つけることが何よりも優先される。
加ヶ知はマキを最後に見た場所に訪れた。セルペンテの扉にはCLOSEの札が掛かっているが、気にせず扉を開く。確かに内装は何者かが暴れたような跡はあるが、殆ど元通りになっていた。片づけが早い。
ドアを開いた音に気づいたのか奥から香が現れた。
「あらぁ、鬼灯様。今日は臨時休業ですわ」
「どうやらそのようですね。お怪我はありませんか」
「唐瓜くんと茄子くんがすぐに捕らえてくれたから大丈夫よ。従業員も全員無事よ」
「マキさんのことですが」
「彼女は今日はもう帰しましたわ。他のキャストも暴漢に怯えていたようで、今日はもう営業を続けることはできないと判断しましたの」
「では現在のマキさんの居場所は知らないと」
「ええ。……彼女に何かございましたの?」
香は深刻な顔で加ヶ知を見つめる。
「マキさんを見失ったと彼らから連絡を受けました。どうやら貴重品も含め一切の持ち物をここに置いているとのことですが」
「あら、あの子たち奥に入ったのかしら。彼らに勝手なことしないようきつく言ってもらってよろしいかしら。”加ヶ知様”?」
「……分かりました。他の従業員に迷惑をかけないよう行動することを伝えておきます」
「マキちゃんには裏から通じる階段から、屋上へあがり、隣のビルへ移って逃げるように伝えましたわ。彼女がその通りに動いているのなら、隣のビルに渡って階下に降りた。それ以後は存じ上げませんわね」
「隣のビルの構造から、屋上から一直線に降りたとなれば、裏道に出ますね。大通りは逃げるには目立ち過ぎますから、大通りに出ず裏に逃げたと考えて間違いないでしょう」
「裏……、というと北の方角ですわね。そっちのほうはホテルしかないわ」
「いえ、北東に行けば中国人街があります。マキさんが中国人であるという情報が正しいのであれば、そちらに知り合いがいてもおかしくはない」
「まぁ、彼女、中国出身なの?」
「信憑はわかりません。私は彼女がどこで生まれようが気にしていませんが」
「貴方はそういう方ですものね。黒服に中国人街の存在がばれてしまったら大変ね」
怪訝な表情をした香に加ヶ知を一抹の不安を覚える。
「それは、どういう意味ですか」
「黒い服で全身を固めた襲撃犯の会話……全て英語で会話していましたわ。全てを聞き取ったわけではないのだけれど、どうやら中国人の女性を探しているみたいだったわ」
「まさか、奴らの探している人とは」
「何か心あたりのある話ですの?」
「ここ最近衆合街に出没する海外組織が居るんです。彼らは人を探してキャバレーやクラブを襲撃しているようです。彼らの特徴は全身黒い服。襲撃犯の恰好と一致する。お香さんの聞いた会話から推測するには探しているのは中国人の女性。マキさんが巻き込まれる可能性が大いにあります」
「でもマキちゃんを見ても襲撃犯は何も反応を示さなかったわ」
「誰が中国人で誰が日本人なんて分からなかったのでしょう。極東に長く住んでいるわけでもないなら見分けることができないのはよくある話です」
マキの行方を探しているのにEUの目的が分かってしまった。EUの狙いがマキ本人でなくても、彼女に危険が及んでいることには変わりない。事態は一刻を争う。
「私は中国人街へ行きます。また襲撃される可能性もあります。どうか気をつけて」
「ええ。鬼灯さまも」
極楽満月の店主は中国人街の住人の中では珍しく日本が好きなようで従業員に日本人を雇っている。何よりも女性が好きで、連日連夜飲み歩いているとか。しかし今日は、飲み歩きをせず、自らが構える店にいた。
「業務を放り出してオンナノコのところへ行くなんてねえ。仕事熱心な僕にはできないよ」
「それってどんな感情ですか?」
「うーん、很无聊」
「それは今あなたが何もやってないからでしょうが!手が空いてるなら掃除でも手伝ってください!!」
「何もやってないは心外だなぁ、桃タローくん。僕は人を待っているの」
「誰をですか?今日はもう来客の予定はないはずって言ってたじゃないですか」
「桃タローくんはたぶんこの中で一番何も知らないんだろうね」
「あなたが何も教えてくれないからでしょう。……この中、ってほかに誰がいるんですか?」
「ほら、アレ」
白澤が指差した先は店の入り口で、そこには加ヶ知が立っていた。
「うーん。好时机。待ってたよ、鬼灯組、組長」
加ヶ知はお構いなしに置いてあった椅子に腰を掛ける。
「まさか2日連続で貴方の顔を見るとは思っていませんでした。さあ、あなたの知っていることを吐いてもらいましょうか」
「まさか拷問する気?そんなことしなくても話すよ。だって厳ついヤローどもに殴られるより可愛い女の子にビンタされたほうが嬉しいもん」
「拷問の手間が省けるのなら兆畳です。さあ話してください。桃瀬真黍について知っていることを全て」
「マキちゃんのことかあ。お前も災難だな。手に入れたはずの娘がいとも簡単に離れていったんだもん」
「……彼女は今日少々辛い出来事が起こりましたからね。私のような人間とは関わりたくない日もあるでしょう」
「でもあんたはいまここでマキちゃんについて嗅ぎまわっている。それに僕のところへ来たということは彼女の過去を聞いたってところか?知ったうえでこんな行動をするなら僕はお前を軽蔑するよ。ヤクザっていうのは義理を最も大事にするって言うけど、やっぱり金や権力でなんでもねじ伏せる奴らなんだな」
「私の立場については今は関係ないでしょう。早くマキさんについて」
「僕はマキちゃんについてお前に話すことはない。質問するなら別のことにしてくれ。そういえば最近いい店見つけたんだよ」
「貴方とはいずれやり合わなければならないと思っていた」
加ヶ知は椅子から立ち上がり、壁にもたれかかっていた白澤のほうへ歩み寄る。その時の彼の表情は殺気に満ち溢れた鬼そのものだと桃太郎は思った。
「奇遇だね、僕もだよ」
白澤は薄い笑みを浮かべる。
「ちょっと、ここでケンカはやめてくださいよーっ!」
桃太郎は心の底から言葉を発したが二人の耳には届かなかったようだ。そのとき
「あれっ、加ヶ知さま!?」
まさに一触即発、危機一髪。すんでのところで放たれた清涼剤。声の主は紛れもない。加ヶ知がいままさに探していた女性、マキそのものであった。彼女は店の裏口である扉から少しだけ顔をだした状態で立っていた。
「ああ、マキちゃん。どうかしたの?」
永劫と感じる静寂を破ったのは白澤だった。
「えっと……お店のほうから大きな声が聞こえたから……、ケンカって言ってたし。ケンカなら止めなきゃ思って……」
「マキさん、私はこの店の常連です。何もここに強盗しにきたわけではないですよ。安心してください。貴女が思うような最悪の事態にはなりませんよ」
いやいやいままさに史上最悪なことが起きようとしていましたよ。桃太郎は喉まで出かかっていた言葉を飲み込む。今はこの場を収めるのが最適である。
「ごめんなさい、お話を邪魔してしまって。マキはもう戻ります」
「ああうん。おやすみ」
白澤の言葉を受けながら裏口の扉は閉まった。白澤はすぐさま扉へ向かい、音を立てないようゆっくりとサムターンを回した。耳を澄ませなければ聞こえない程の錠の音が鳴ると手頃な段ボール箱に腰かけた加ヶ知が口を開いた。
「質問を変えましょうか。貴方はマキさんのなんなのですか」
「誤解されないためにもこれには答えなきゃいけないね。彼女は僕の姪。妹の子だ。彼女の両親……僕の妹が死亡してからは僕が彼女の養育費を工面していた」
白澤の言い分はこうだった。彼女は白澤の妹と日本人の男性の間に生まれた。10年前とある事情で中国から移住してきたのだが、3年前に両親が不慮の事故に遭ってしまい帰らぬ人となった。それ以降はすでに日本に住んでいた白澤が、彼女の面倒を見ることとなった。彼女を大学に進学させることは両親の夢であったため、高校中退はせず、進学の道を選んでいた。さすがに白澤だけでは大学の授業料を払うことはできなかったため、彼女に自分で工面するように伝え、アルバイト先を紹介した。それ以降彼女と会うのは殆どキャバレーだけになっていた。退学をしていたことは白澤も知らなかったらしい。桃太郎曰く、彼女とこの店で出会ったことはないとのこと。
「マキちゃんはたびたび中国出身であることをからかわれていたみたいだ。彼女は日本に溶け込もうと必死だったんだけどね。今はもう中国語はすっかり忘れてしまっているよ」
「その、移住する理由となったとある事情というのはどんなものか知っていますか」
「んー……、確か旦那関連だったかな。仕事だったか家族のことだったか忘れた。……そんな目をすんなよ、10年前だからけっこう忘れてんだよ」
「マキさんとは両親が亡くなる前から関わりがあったのですか?」
「両親のほうはそうだけど、なんせ10年前のマキちゃんは小学生だからね、初めて顔を見たのは中学生だったか、高校生だったかな。今とそんなに変わらないけどあどけない感じが残っててさー、あ、写真あるよ。見る?」
「この話が終わってから必ず見せてください。彼女や彼女の家族が海外マフィアに襲われるようなことは今までにありましたか?」
「マフィアあ?なんでマキちゃんがそんな物騒なものに関わっていなきゃいけないの。大方お前が巻き込んだんだろ。これ以上危険に曝すようなら警察に言うぞ」
「小学生の脅しですか、まったく。彼女が極楽満月に来た理由はご存知ですか?」
「詳しくは教えてくれなかったけどセルペンテでなんかあったって聞いた。あと暫くここにいさせてくれって」
「彼女は自分の立場を理解しているのでしょうか……」
「思い当たることがあるなら教えろ、こっちは情報を提供したぞ」
「まだ確証の取れていないことは情報としては不十分です。一つ言えるのは、彼女は何者かに狙われている立場である可能性があるということでしょうか」
「……はあ!?お前何やったんだよ!!」
「あの、そう言い切れる根拠ってなんですか?」
すかさず桃太郎が仲裁の体制をとる。
「一つは、ここ最近海外マフィアがこの街に現れていること、二つは昨日セルペンテに何者かからの襲撃があったこと、三つはセルペンテに現れた襲撃犯は中国人の女性を探していたこと。それだけです」
「その中国人の女性っていうのがマキさんかもと……。確かめる手段はあるんですか」
「襲撃犯の身柄はこちらで確保しています。いまは子分が”話をしている”ところですから……時間の問題です」
「ふぅん……」
白澤は加ヶ知の話を一通り聞いたあと何かを考えているようだった。しばらくして、加ヶ知に対してこれからどうするのかを訊いた。対して加ヶ知は返事の代わりに椅子替わりにしていた箱から腰を上げた。それを見て大方、事務所に戻り子分から話を聞くのだろうと白澤は察したのだが、加ヶ知は白澤の思いがけない方向に向かった。
「マキさんは2階にいるのですよね」
白澤が先ほど鍵をかけた裏口の扉の前に立った加ヶ知はぽつりと呟く。
「マキちゃんに何をするつもりだ」
「話を聞きます」
「彼女自身が親の職業を知らないんだぞ。お前にとって有益な情報が手に入るとは思えない」
「大きな情報は期待していません。必要なのは散らばった情報を繋ぐ、『糸』です」
「僕が止めても桃タローくんが止めてもお前は行くんだろうな」
「ええ、そのつもりです」
「部屋にあるものを壊したりするなよ」
「話を聞くだけです。そんなことはしません」
「……。そうだね」
加ヶ知は裏口の扉を開き、振り向かずに奥へ行った。
扉が完全に閉まったのと同時に白澤は桃太郎に話しかける。
「さ、桃タローくん。僕は外行ってくる」
「えっ!お店はどうするんですか」
「今日はもう終わり。明日は開けられないかもねー。店じまい、しといて」
「ちょっと待ってくださいよ、白澤さん!」
桃太郎の呼びかけはむなしく、派手な灯が点しつつある街へと消えた。
過去と再会する
速足で2階の部屋に向かう。ここは普段伯父である白澤さんが住んでる部屋とは別に物置として使っている部屋で簡易的なベッドがある以外は段ボール箱や変わった匂いのする植物の葉っぱや根が入った容器が所せましと置いてある。私は漢方薬のことは全く分からない。この部屋に入るたび、私は伯父さんのことも、お母さんのことも何も知らないと思ってしまう。ベッドに体を預けたところで心臓が不自然に早くなっていたことに気づいた。私が店をすっぽかしたから、加ヶ知さんはきっと怒っている。偶然とはいえ、ここにいることがばれてしまったなら、もう長くはいられないだろう。荷物という荷物も持っていないけれど、どこか別の場所に行く他ないだろう。伯父さんや桃太郎さんには申し訳ないけど。でもどこに行けばいいのだろう。
コンコン、と戸を叩く音が聞こえた。私が返事するより先に扉が開いた。入ってきたのは加ヶ知さんだった。私は固まった。
沈黙を破ったのは加ヶ知さんだった。
「1階の店主が、マキさんがここにいると教えてくれましたので」
「ぅぅ……誰も通さないでって言ったのに……」
「そうでしたのか。すみません。特に止められなったので」
「えぇ……嘘ぉ」
加ヶ知さんはベッドに座ったままの私の隣に座った。顔をじっと見つめられる。正直言って、とても怖い。
「あなたは中国出身と聞きましたが、本当にそうなのですか?」
唐突に質問を投げかけられ、再度固まる。
「えっと……、その話、どこで訊いたのですか?」
「貴女の伯父を名乗る方からです」
ああ、やっぱりそうだよねー。あの人どこまで話してんだろう。警察に捕まった犯人が尋問を受けているときってこんな気持ちなんだろうか。
「私は確かに小さい頃は中国に住んでいたのは確かです。お母さんとは血は繋がっていないと、母本人に聞きました。本当の母親は私が生まれたのとほぼ同時になくなってしまったそうです。私を生んだ母親は日本人です、なので伯父さんとは血は繋がっていないんです」
「それでもあの人は貴女の両親が亡くなった後あなたの後見人をしてくれたのですね」
「中国から日本に来たのは中学生になるときです。今から3年前に両親が車の事故に遭って、それから伯父さんや桃太郎さんにお世話になっていました。日本に来てすぐは日本語がうまく話せないのを、同級生にからかわれていましたが、二人が一生懸命教えてくれて、今はもう中国語が話せないくらいで。大学進学は両親の希望でもありましたから、進学しましたけど、1年もせずに辞めました。同期や先輩にいじめられていられなくなったからです。私が衆合街にいるところを見たことをネタにして色々噂を流されたんです」
自分の過去をこうやって話すのは初めてだった。今まで誰にも話したことはなかったけれど、加ヶ知さんになら話しても蔑まれることはないと思った。誰かに聞いてほしかったのかもしれない。そう思うと顔が熱くなって、気がつけば涙を流していた。加ヶ知さんは何か考える様に黙っていた。
「私だって……普通の学生生活を送りたかった。みんなに溶け込めるように、日本人になれるように、頑張ったけど……駄目だった……普通になりたかった……!」
目の前が真っ暗になる。同時に暖かいものに包まれた。独特な煙草の匂いとすぐ傍から加ヶ知さんの声がする。
「辛い話、させてすみませんでした。嫌なことを思い出させてしまったでしょう。泣いていいんですよ。私しか見てませんから」
決壊した川のように涙が溢れてくる。言葉も分からないくらい喚いて、頭の中もぐしゃぐしゃで、たぶん誰にも見せられないくらいひどい顔になってるかもしれないのに、加々知さんは黙って背中を擦ってくれていた。
……気がついたら眠ってしまっていたらしい。目の前に炎が広がっている。あたり一面が火の海で、その中を泳いでいる真っ赤な金魚……金魚?
「おっぎゃああああああ!!!!!!」
「あ、起きましたか。おはようございます」
「お、おはようございます……。なんで裸なんですか」
目の前にいた加々知さんはいつもはきっちり着込んでいるスーツの上半身を脱いでいた。二の腕から背中にかけて、びっしりと刺青が入っている。炎や針山の、地獄みたいな場所で泳ぐ、金魚の絵だった。
「あなたが私の服を離さなかったので仕方なく、です。顔を洗ったら、1階に来てください。作戦会議をします」
私は初めて、ここで自分が加々知さんの服を手に持っていたことに気づいた。慌てて加々知さんに差し出す。
「作戦会議って何のですか?」
「これから起こる事件についてです」
事件?
「あっ、スーツ汚してしまってすみません。クリーニング代は出します」
「いえ、結構です」
洗うなんてとんでもない、と聞こえた気がした。洗えないタイプのスーツだったのかな。
「弁償……します……」
「スーツのことなら気にしないでください。セルペンテに置いていた鞄はこれで間違いないですか?」
「あ、はいそうです」
「貴女のものか確かめるために中身を確認させてもらいました。盗ってはいませんが無くなっていないか確認してください。それが終わったら、早く顔を洗ってきてください」
「えぇっと、はい……」
加々知さんから手渡されたバッグの中身を見てみれば、中身は全部無事だった。中から化粧直しの道具を取り出して洗面台へ向かう。洗面台の鏡に映った私の顔は、確かにお化粧は殆ど落ちてしまって、目は赤くなってはいないけど涙の跡がくっきりと残ってしまっていた。顔を洗って、最低限の化粧をする。伯父さんも桃太郎さんも、私のすっぴんを知っているから、まだいいから、加々知さんの近くにさえ座らなければなんとかなるだろう。意を決して、1階に降りた。
「高校の卒業アルバムとそんなに変わらないですね。少し化粧していますか?ノーメイクでも見たかったです」
私が1階の極楽満月に入ってすぐ、ちゃんとスーツを着込んだ加々知さんは、しっかり私を見てそう言ったのだった。
「なんで高校のアルバム見てるんですか!?」
「僕が持ってきた」
何でもない顔で伯父さんが言う。
「なんで!??」
「あ、これ、体育祭の写真」
「ほう、これは……」
「ぎゃああああああ!!!!!!」
急いで机の上に広がっているアルバムを閉じる。加々知さん、がっちり掴んでるな……力が強い。
「あの、作戦会議は」
「そうですね、マキさんが来ましたし、始めましょうか」
加々知さんはアルバムから手を離して、私を四角いテーブルの真正面、白澤さんの隣に座らせた。テーブルから少し離れた場所にある椅子に桃太郎さんが座った。
「マキさんの名字は、『桃瀬』で間違いありませんね?」
「はい、そうです。桃瀬真黍です」
「父親はこの方で間違いありませんか?」
そう言って加々知さんは私の前に運転免許証のコピーを見せた。それは確かに父親のものだった。
「間違いありません……それが、何か?」
「情報はこれで全て揃いました。マキさん、父親の仇を取りませんか」