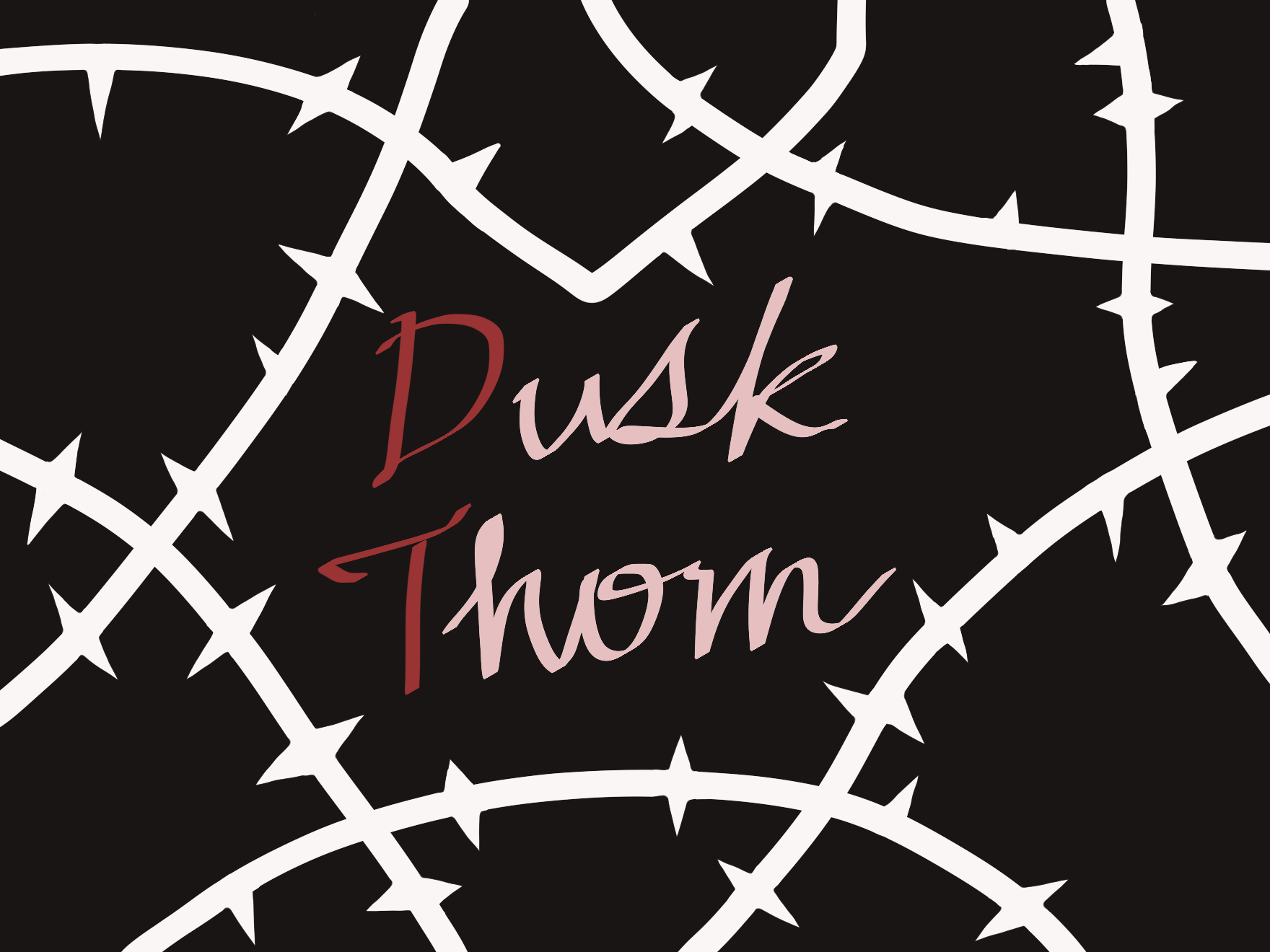クラブ「セルペンテ」
クラブ「セルペンテ」は大通りから見えるビルの2階にあった。恐る恐る扉を開けてみると、きれいな和服の女性が迎えてくれた。
「いらっしゃい。あなたがマキちゃん?」
「はい!よろしくお願いします!」
「そんなに緊張しなくていいのよ?さあ、中に入って」
内装は小さいけれど装飾は高級感にあふれていて、場違いな場所に来てしまったと思った。
「今までのお仕事と違うところも多いはずだから、少しづつ慣れていってね。私のことはお香、って呼んでいいわよ」
ここは会員制のクラブで「知る人ぞ知る」を好んでいる人に気に入られているらしい。本当に私はここで働いてもいいのかな。加ヶ知さんは向いているって言ってたけど、今までと世界が違い過ぎてここで働いている自分が想像できない。
もともと今日は定休日だったから、1日全部使ってお香さんに色々仕込まれた。すごく柔らかい雰囲気だけど、仕事に関してはとてもストイックな人みたい。一通りした後はもうへとへとだった。
お香さんの指導を書いたメモ帳を確認していたら、誰か入ってきた。私とあまり身長の変わらないスーツの二人組。一人はつり目の黒髪で、もう一人はたれ目の薄い髪色。今日はお店が開いてないはずだけど、ボーイかな。お香さんが困ったように入口にいる二人組に近づいた。
「あら、二人とも。『CLOSE』の看板、見えなかったのかしら」
「いえ、今ここに”マキさん”がいるという確認をしに来ました」
黒髪のほうが答える。
「まぁ、加ヶ知様も大変ねぇ。明日から出てもらう予定だったから、二人に練習台になってほしかったんだけれど」
「そんな!俺たちが”マキさん”の最初のお客さんになったら兄貴から何されるか……!」
「それは難儀ねぇ……」
お香さん!明日からとか聞いてないんですけど!!んでその二人は誰なんですか!?色々と質問したいことを抱えて私も入口へ向かう。
「あっ、マキちゃんだ~。近づいてみるともっと可愛いね~」
「おい、馬鹿茄子!”マキさん”だろ!」
ここで初めてたれ目のほうが喋った。それに黒髪のほうがが諌める。なすび、と呼ばれたたれ目のほうはごめん、と軽く謝罪をした。
「マキちゃん、この二人は加ヶ知様の舎弟の唐瓜ちゃんと、茄子ちゃんよ」
舎弟、って確か後輩的なやつだよね。やくざやさんに対して敬語を使わないお香さんの正体は一体誰なんだ。加ヶ知さんの奥さんとかなのかな。
「マキちゃん…”マキさん”のこと、2か月くらい前から見てたよ!」
「えっそんなに前から……あと、無理してマキさんって呼ばなくてもいいです。マキちゃんって呼ばれたほうが気が楽だし」
「ほんとう!?マキちゃん、俺らとあんまり歳変わんないしね~。よろしくね」
「すいません、コイツなれなれしくて……」
「じゃあ休憩もこれくらいにして、マキちゃん、次に行きましょうか」
えっまだやんの!?
「まだまだ違いに戸惑うことはあるんですけどねー」
めでたい初出勤日。私が話しかける相手は、もちろん加ヶ知さん。
どうしてこうなってしまったんだろう。裏道歩いてたらやくざに目をつけられたとかどんなフィクションだよ。ミキちゃんだったら信じてくれるかな。
加ヶ知さんは黙って私の話を聞きながら、13年製のカナディアンウイスキーが入ったグラスを傾けていた。ウイスキーってクセがあって飲みにくいんだよね、スコッチは特に。カナディアンはまだましなほう。加ヶ知さんはスーツから煙草の匂いがするし、相当煙草を吸っているんだろうな。あ、灰皿近くに置いとかないと。
前々から思ってたけど、加ヶ知さんは私とこうやってお酒を飲むのを楽しんでいるのかな。丁度いい女の子を見つけたから、とりあえず接待のマナーを教え込んで、そのあと私が知らないような遠い土地に売ったりしようとか考えてるのかな。この人相ならやりかねないっていうかー……やくざやさんなんてできれば関わりたくないなって思うのが普通だし、はぁ。どうしてこんな状況に私はいるんだろう……
「あなたを身売りしようなんて考えてないですよ」
「エスパー!?」
「心の声が漏れ出てましたので、訂正したまでです。私はここで働いてほしかったんですよ」
「ふーん……。あっ、そういえば、さっきからアタシばっかり喋ってますね!すいません」
「いえいえ、マキさんの話は聞いていて面白いですよ」
「そういえばマキ、加ヶ知さんのことあんまり知らないです。しゃてい?に茄子くんと唐瓜くんがいるのは聞いたんですけど」
「確かに仕事の話はできないものも多いのでしないですね。プライベートはあってないようなものですので……する話がないです」
「ご家族とかはいらっしゃるんでしょう?お香さんとか」
「彼女は兄弟でも何でもないですよ」
「えっ、奥さんじゃないんですか」
「違いますね。独身です。バツもないです」
お香さん、いったい何者なんだ……
「マキさん、今度着物を買ってあげましょう」
「あー……今着てるのは前の店にいたときから着てるものですしねー。確かにこの店には合わないかもしれないですけどー」
「何かプレゼントをしたいと思っていたのでちょうどいいです。……しかし、明日は終日予定がありますので別の機会になってしまいますが」
「お仕事大変ですね」
「代わりにあの2人をこちらに向かわせるので心配する必要はないですよ。終わり次第こちらに向かいますので」
「わーいマキまってます」
やっぱりこの人から逃れられることはできないのか……
「マキちゃ~ん、来たよ~」
開店と同じくらいに茄子くんと唐瓜くんが来店した。
「兄貴は今日連合の会合に参加するから来れないんだよ」
「アタシはよくわからないけど、加ヶ知さんは大事なお仕事なんですね」
「茄子、あんまりこういう話はしないほうがいいぞ」
とまぁ、2人とは友達と一緒に飲んでいるような、共通の知り合いの話題で盛り上がっていた。これはクラブの接待としてどうなんだろう。
「ゲストが楽しくお酒を飲める場所がクラブよ。もっと堂々として」とお香さんは初日に言ってたっけ。
堂々と。自信を持って……意識すると難しいな、これ。
2人はこの世界に入ってまだ日が浅いらしい。雑用が主だけど加ヶ知さんから直々に仕事を貰えているから悪い気はしないそうだ。
「でもさ~最近まで忙しかったよな」
「確かに、取り立てをいつもより厳しくしろって言われたし、その上でマキさんを監視しなきゃいけなかったしな」
「シフトなんて分からなかったからさ~来ない日もあったよな」
「あーあった、あった。報告したら加ヶ知さんすごく怖い顔してたし……それからもっと大変だった」
「今はお酒飲みながらできるからいいよな~」
2人はいい感じに出来上がってしまったらしい。こんなこと言っても大丈夫なのかなー。昨日、加ヶ知さん、終わりしだい来るって言ってたけど。
そのとき、入口が大きく開いた。加ヶ知さんかと思ったけど違った。黒ずくめの恰好をした三人の男性で全員サングラスをしていて表情が読めない。すぐさまボーイが近づいたけどお構いなしに入ってくる。
”Find the Chenese.”
“I can’t find her because they are all Asians.”
”Would you like to abduct everyone?”
“No good.We should not be conspicuous.”
日本語じゃない。私は恐怖で固まってしまった。
“We know that she is in Japan. We gotta definitely bring her to Mr.Beelzebub.”
最後の言葉を聞くや否や、茄子くんが男に向かって飛びかかった。一番前にいた男性が懐に手を入れようとして何かを取り出す前に襟をつかんで一本背負いを決めた。黒いものが床を滑る。唐瓜くんがそれを拾い上げて後ろにいた2人に対して腕を突き付けて、……拳銃を発砲した。唐瓜くんの対角線にいた2人が乾いた破裂音とともに太ももと脛から血を出して崩れ落ちる。
何が……起こっているの?
お香さんが私の隣にきて囁いた。
「いい?マキちゃん、裏にある階段から屋上に上れるわ。隣のビルの間隔は狭いから、屋上に置いてある板切れで移動できるの。渡ったらちゃんと回収しておいてね。そこから逃げられるの。捕まったらダメよ?」
これは非常事態なんだ。お香さんの言うことを守って逃げないとダメなんだ。
「私のことなら心配しないで。また明日ね」
私はお香さんに背中を押されて裏の階段に出た。お香さんは、茄子くんと唐瓜くんは。いまここではなにが起こっているのか。何が何だか分からない。でもいまはお香さんが言ったことを守るしかない。
屋上に上がって板を隣のビルにまで掛ける。足元が不安。慣れない草履を脱いでから、隣のビルへと移る。私は一目散に走り出した。この街で、この国で一番信頼できる人のところへ。
「極楽満月」にて
ここ一番の繁華街≪衆合街≫は中央を十字に区切る大通りに沿ってビルが立ち並ぶ。無計画に土地を切り売りし、建物を建てた結果、葉脈のように入り組んだ小さな道が出来上がった。この街の北東には小規模な中国人街が存在する。日本に移り住んだ中国人が追いやられ、人気の少ない場所で店を開かざるを得なくなった結果である。漢方薬局≪極楽満月≫はここにある。
時は少し遡る。
「欢迎光临、ってお前かよ」
「加ヶ知さんこんにちは。今日は何の御用ですか?」
白い衣服を身に着けた中国人の男性と日本人の男性、白澤と桃太郎が、来客に話しかける。加ヶ知さんと呼ばれた男は元来怖いと言われる目つきをさらに怖くしていた。
「二日酔いに効く薬を。すぐに効くやつ。すぐに出せ」
「ぶっきらぼうだな、それが人に頼む態度かよ」
「珍しいですね、加ヶ知さんが二日酔いなんて」
「洋酒はもともと得意ではないんですが……昨日は飲み過ぎました」
「加ヶ知さん日本酒派ですか、俺もですよ」
「日本酒は日本人にとっては血液です」
「確かに生きていくには欠かせないですね」
「僕の話無視ッ!?」
「お前は早く作れ。さもなければ利率を引き上げてもかまわん」
「それとこれとは話が別だろ!?こいつのとこでは絶対に金を借りたくなかったんだけどなぁ。はぁー、可怕的、桃タローくん、こんな人と関わっちゃダメだよ」
「現につるんでるでしょうが」
白澤は手元を動かしながらも口を止めない。
「あそこの店、女子大生キャバ嬢だけを揃えてるってこともあって、けっこう若い子がそろってていいよね~、僕も今夜はあそこ行こうかな」
「彼女は昨日からセルペンテです」
「えっと、あのキャバレー買い取るって言ってましたよね?アレどうなるんですか」
「どうも何も、シノギになるだけです。私はマキさんを自由にできればそれでよかったので」
「セルペンテってあのお香ちゃんのお店か。じゃあ彼女はいよいよアンタの”鳥籠の鳥”になったわけだ」
「あの店を買い取るまで2か月。その間に他の男に取られないか……正直、かなり焦っていました。しかし、もう。その心配はない。やっと手元における。そう思うと酒が進むんですよ」
「一人の女性のために1千万だっけ?傍から見たら狂気だよ」
「数多の女性に貢いだ合計金額なら貴方のほうが多いでしょう。そっちのほうが頭おかしいですよ」
「ここで喧嘩はやめてくださいねー」
「早く薬を出すか口を紡ぐかしろ」
「逃げも隠れもしねーよ。お前が黙れ」
白澤が差し出した包みを加ヶ知は乱暴に取り上げ、代金を差し出す。そのまま足早に店を後にした。
「あれさー。純愛っていうのかな。一途に女性に貢ぐっての」
「今の状況では少なくともドラマにはなりませんね」
会合に向かう自動車の中。
沈黙に耐えかねた閻魔大王が、加ヶ知に話しかける。
「ねえ、鬼灯くんさぁ」
「その名前で私を呼ぶのはもう貴方くらいですね」
「あぁ、確かにそうだねぇ。あとは名前を知っているお香ちゃんくらいだねぇ」
「加ヶ知輝を名乗るときに過去と決別したと思っていましたが……やはり自分を知らない人が増えるというのは寂しいものですね。ところで、何の話ですか」
「えーっと。今君が肩入れしてるホステスの、マキちゃん?あの娘、関わるのはやめたほうがいいと思うよ」
「何を根拠にそんなことが言えるのですか」
加ヶ知の表情が暗くなる。
「実はさぁ、その娘のこと調べたんだよ」
加ヶ知は目を見開いて閻魔を睨む。
「何を!勝手にやっているのですか!いくら私の『親父』といえど!やっていいことと悪いことが!あるでしょうが!」
「子である君だからこそ心配なんだよ!マキちゃんの本名すら知らないんでしょう!?」
マキの本名。確かに聞いたことはない。いずれ聞くことになるだろうし、特に気にすることもなかったが。
「彼女の本名は桃瀬真黍。住んでいるのは衆合街じゃなく焦熱のほうなんだよね」
「焦熱というと電車で乗り換えが必要な距離ですね」
真黍でマキ。安直な名前だが彼女の素直な性格が見える。
「そうなんだよね。一番不可解なのが、1年前に大学を退学しているんだよねぇ」
女子大生を名乗っていながら大学を中退。住んでいる場所が繁華街でなく少し離れたビジネス街。おそらく親父は『ほかの男がいる可能性があるから彼女を隣に置くのは諦めろ』と言いたいのだろう。
「だから何だと言うのですか。いずれ彼女は私に振り向くはず」
「その自信はどこから来てるの?彼女はすでに両親を亡くしている在日中国人なんだよ。こっちの世界の人間と通じている可能性があるんだ。まだ確定じゃないけどうちのシマを狙わんとする奴らの手先かもしれないよ。そんな子を君が気に入っているっていうことが知れたら」
「貴方はどれだけマキさんを敵視すれば気が済むのですか。彼女は堅気ですよ。杞憂です」
明らかに機嫌が悪くなった加ヶ知を見て、そうだといいんだけどね。と閻魔は一人思う。彼に諦めるよう促したのはただの疑心からではない。しかし確定的な証拠を見せるにはまだ尚早である。いずれ本人の口からきくのが一番だろう。おおよそ極道とは思えない見た目をしている彼だが、仮にも十王連合の総裁を務めているのだ。人の扱い方は慣れている。加ヶ知の良いとは言えない表情から、これからの衆合街の未来を案ずるのだった。
つつがなく会合は終了し、加ヶ知は衆合街にある事務所に戻っていた。
自宅はあるが帰る気力がない。マキさんに会いたい。彼女に会ってからならこんなに疲れることもなかっただろう。今からでも会いに行こうか。彼女ははにかみながらも膝枕をして自分を労わってくれるだろう。重い体を動かしながら廊下を歩くと、後ろから呼び止められた。今夜事務所の電話番をしていた子分だった。用件を聞けば先ほど茄子という男から電話が来ていたという。確か彼とその「兄弟」唐瓜はセルペンテに向かわせていた。マキさんの身に何かあったのだろうか。伝言はないかと聞こうとした矢先に、今まさに話題にしようとしていた2人の小柄な男が息を切らして加ヶ知の前に現れた。
「あ、にき……、マキさん、来て、ませんか……?」
「マキさんがうちの事務所を知っているはずがないでしょう。それに彼女のようなかわいらしい女性がここを訪れるなんて、道に迷ったときぐらいですよ」
それは違うと思います、と唐瓜は心の中でツッコむ。
「さきほど、セルペンテで……襲撃が、あって……ママが、マキさんを、店の外に逃がしたのですが……それから、マキさんの居所がつかめなくて……とりあえず、襲ってきた奴らは俺たちが拘束しておきました」
「まず襲撃犯はここに連れてきなさい。そしてマキさんの捜索へ。自宅の場所は知っていますか」
「いいえ、知りません。探すんですか」
「彼女の家は焦熱にあります。そこへ向かっているタクシーの中を確認するか、駅まで向かうほかはないでしょう」
「アッシーくんを呼んでたらもうダメだなー」
茄子が頭の後ろに手を回しながらつぶやいた。
「でも、マキさんは持ち物を店に置きっぱなしだぞ、テレカをずっと持ってるならともかく、財布がなきゃ電話も使えないじゃないか」
それを聞いて加ヶ知ははっとした。
「どうしてそれを先に言わないのですか!街の外に出るお金がないのなら、彼女はまだ衆合街です!今すぐ探しなさい!場所が狭まったのなら探しやすいでしょう!」
「こんな人込みの中探すのが大変なんですよ……あれ、兄貴は探さないんですか?」
「私は、寄るところがあるので」
加ヶ知は事務所を後にした。