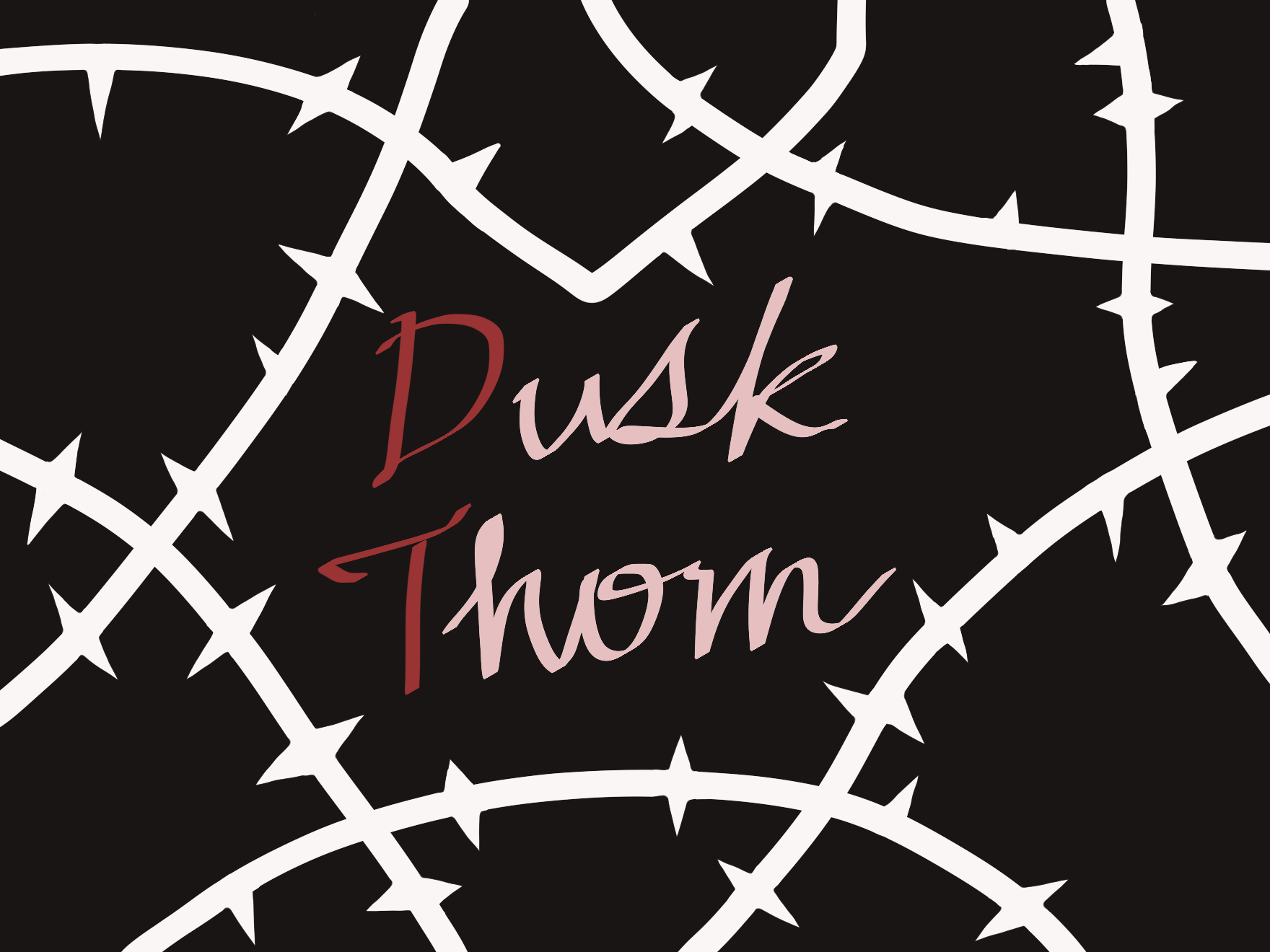極道加々知さんと女子大生キャバ嬢マキちゃん
繁華街の端っこにあるキャバレーが、アタシのアルバイト先。
アタシがこのアルバイトやってるのは、ブランドの高いアクセサリーとか、ドレスとか着れるし、
いいお酒もいっぱい飲めるし、周りのナウい大学生はみんなやってた、ってのもある。
成績上位にはなったことはないけど、それなりに楽しくやってる……はずだった。
今日も、いつものようにアルバイト先に向かって支度をしているとと、ピリピリと緊張した雰囲気が漂っていた。
アタシは、先に来ていたミキちゃんに駆け寄って、小声で訊いた。
「ねぇ、なんか今日、いつもと違くない?」
「あぁ~、たぶん、さっき来たお客さんのせいかもしれない……」
「いつもみたいにニャーンって言わないんだね」
「いいじゃん、バックヤードぐらい~」
「で、どんなお客さんなのか見たの?」
「うん……VIPルームのほうに歩いていくのを見ただけなんだけどね、
コッチの人だよ、たぶん」
ミキちゃんは人差し指でほっぺたを二回撫でた。
「すごい高そうなスーツ着てたし……顔怖いし……来た途端に店長と支配人が飛んできてたし……
顔怖いし……」
「へーそんな人が来てるんだー」
「興味ない感じニャン……」
「だってVIPルームに行くような人なら、ナンバーワンの娘を指名するだろうしーアタシには関係ないしー」
「まぁ確かにそうかもねー」
あはは、と2人で話してたらいきなり店長が入ってきて、怖い顔をしてアタシのほうに向かってきた。
「ママママキちゃん!!!何やらかしたニャン!?」
「まだ何もしてないよ!今さっき来たばっかりだし!えっと、店長さん、どうしたんですか?」
「加ヶ知様がマキちゃんをご指名なんだよ。ご来店されるなりマキちゃんの写真を指差してさ……準備終わってるならすぐ席についてね」
「……加ヶ知、さま?」
「うちのケツモチ、鬼灯組の組長さんだよ!こんな場末のキャバレーに来るなんて、きっとみかじめ料のことに決まってる……!マキちゃん!うちの店の存亡がかかってるんだよ!」
「えっ、鬼灯組の組長、ってことはあの閻魔會の若頭さんですか!?」
「まってまって、ほーずき組ってナニ!?えんまかいってナニ!?」
「……マキちゃん……」
ミキちゃんが憐れんだ目で見ている。店長が呆れた顔をしている。
「とりあえず、加ヶ知様はうちのお店にとってとっても大事なお客様なんだよ、だから、頑張れ!」
「ファイトニャーン……」
「えええ……行ってきます……」
よくわからない声援を背中に受けて、アタシは初めてのVIPルームへ向かった。
「ご指名ありがとうございまーす!マキ…でーす……」
いつものように笑顔を向けたんだけど、相手の顔を見てしまった瞬間に顔がこわばってしまった。
何あの表情、人殺したことあるよ!きっと!っていうか睨んだだけでチンピラ100人くらいは普通に土下座するでしょ!この人絶対敵にしちゃいけない人だ、味方になっても困るけど!
「待ってましたよ、マキさん。座ってください」
「あ、は、はい!失礼しまーす……」
周りの女の子からの視線が怖いよ~、笑えているかな、アタシ。
「加ヶ知様、ですよね。えっと、何飲みます?やっぱシャンパンですか?ほーずき組の組長さんなんですよね、もっと高いのとかいっちゃいます?」
「マキさん」
「ひゃいっっ!!!」
「あなた、ここに来るまでに大通りから裏道を通って来てますよね」
裏道……。ここの繁華街、衆合街は入り組んだ形になってて、車が通れるくらいの十字型の大きな通りに沿ってビルが並んでいる。そこから建物の隙間に人が1人2人くらいなら並んで通れるくらいの裏道が枝みたいにいくつも絡まっている。
ここのキャバレーは大きな通りからでも行けなくはないけど、裏道から通ったほうが近道だから、いつも裏道を通って通っていた。でもなんでいきなりその話?
「あそこはほかの裏道と比べて入り組んでいて人目に付きにくいですから、あなたのような女性が通ると危ないですよ」
「はぁ、へーそうなんですね、ありがとうございます。え、まさかそのためにご指名……」
「最近何かと物騒ですからね、自分の身は自分で守れるようになるべきです。よくない人に捕まってしまいますよ。私のような」
腰に手をやられて引き寄せられた。肩が触れた。っていうか密着された。耳に息がかかる。
「おっぎゃああああああ!!!!!!」
アタシの人生、終わったと思った。
マキの災難
「あ、さっきの叫び声いいですね、もっと聞きたいです」
叫び声を耳元で聞いてなんだそれ!趣味悪っ!
「すみません、加ヶ知さま……当店はおさわり禁止となってます……ので」
私がこの店をアルバイトに選んだ理由は女の子へのノルマが他より少ないことだった。ほかの店は同伴を強制させてたり、風俗嬢みたいなことをさせていたりするらしい。噂でしか聞いたことないけど。
加ヶ知さんはそうなんですね、と言って腕が名残惜しそうにアタシの体から離れる。案外あっさり引いてくれた。よかった……
そのあと加ヶ知さんとどんな話をしたか覚えていない。気が付いたらバックヤードの壁とぶつかっていた。
ミキちゃんに聞いたらうわごとを言いながらフラフラとバックヤードに戻ってきたらしい。
しばらく放心状態になっていたら、店長がもう退勤していいって言ってくれた。
こんな集中力を使ったのは何年ぶりだろう。今日はもう出れる気がしなかったから、店長の言葉はありがたかった。
次の日も加ヶ知さんは来店してきた。そしてさも当然のようにアタシを指名してきた。
店長はアタシを褒めてくれたみたいだったけど、それよりもほかの女の子からの視線のほうが怖い。
そりゃそうだよね。ナンバーワンになったことない女の子があんな凄い人に指名されるなんて、普通じゃありえないもんね。
開店前に店長から、色々と教えてもらった。加ヶ知さんのこと、鬼灯組のこと、閻魔會のこと。閻魔會っていうのは裏社会の中でも広い勢力を持っている。その会長閻魔大王は裏社会の同盟の総裁も務めているらしい。その閻魔會の若頭、所謂ナンバー2が鬼灯組の組長、加ヶ知さんというわけ。そしてこの衆合街は鬼灯組のシマってこと。よくわからなかったけど、要は加ヶ知さんはこの店にとって大事にしなきゃいけないお客様だってことはわかった。
「今日は裏道を通らなかったんですね。約束を守れるのは良いことです」
加ヶ知さんはアタシが差し出したスコッチウイスキーのロックを傾けながら話し出した。なんでそれを知っているんだろう、この人。
「はい、今日は大通りを通って出勤してきました!いつもより早めにアパートを出たんですけど、早過ぎたみたいで、早く着いたんですよね~」
「今日も裏道を通ってきたら攫ってやろうかと思いました」
シャレになんねぇ!!
「冗談ですよ」
いやいやいや。
「もしかして加ヶ知さま、あの通りを見張ってたんですか?」
「ええ、その通りですが」
「嘘だろまじか」
「実際は私ではなくて、私の舎弟……ですね」
やくざって人を見張る職業だっけ?
「それはそうとマキさん、明日からここに来なくてもいいですよ」
「え?それってどういうことですか」
「明日からは別の場所で働いてもらいます」
「いやですいやですいやです!アタシそういうの無理ですから!」
「場所はクラブ『セルペンテ』です。ここよりも条件はいいと思いますよ」
「クラブですか?キャバレーじゃなくて?」
「あなたにはそちらのほうが向いてると思いまして。悪いことはないです。給金も増えますし」
「おきゅうきん……あれ?なんで加ヶ知さまがこんなことできるんですか?」
「私、オーナーなんですよ。ここの」
びっくりしすぎて変な声出た。オーナーがいたなんて聞いたことない。だったらなおさら、アタシを指名する理由がわからない。
「まぁ詳しいことは支配人にでも聞いてください。ほら、マキさんも飲んで」
「あ、はい。いただきまーす」
アタシこれからどうなるんだろう。ホールに流れるビッグバンドの軽快な音楽と裏腹な気持ちがアタシの中を渦巻いていた。
閉店準備が終わった後、アタシは支配人に呼び出され事務所にいた。
「マキちゃん、急だけどここで働くのは今日で終りね」
「アタシ、まだ納得してないですよ!これからどうなるんですか!?」
「マキちゃんはここよりクラブのほうがやりやすいんじゃないかってことで、そっちに移動してもらうんだよ」
「理由になってないですよ!そもそもこんな若い人がいていいところなんですか?クラブって」
アタシに恥をかかせて笑いたいのかもしれない。
「こっちとしては大通りのキャバレーの女の子を何人か引き抜くって条件だったからさ。マキちゃんもいろんなところで働ける機会ができたって思えばいいよ、社会勉強になるよ」
何度問いてみても、結局答えは全て「加ヶ知さんの考えだから」だった。アタシはどうあがいても、明日からは「セルペンテ」というクラブで働かなくてはいけないらしい。
「加ヶ知さんがここのオーナーだって知りませんでした。なんで教えてくれなかったんですか」
「教えるもなにも、今日いきなりさ。事務所に大金持ってきて『これでここを買い取ります』だよ。こっちだって寝耳に水さ」
今日いきなりここを買い取った?なんでそんなことを?アタシに対しての加ヶ知さんの謎は深まるばかり。
事務所を後にしたとき、ミキちゃんが心配そうにしていた。どこかでアタシが今日限りで辞めることを聞いたそうだ。この店に嫌気がさしたのか、とか、アタシの為にできることはないか、とかいろんな質問をしてきたけど、正直アタシのほうが知りたい。どうしてこうなったんだろう、って。ミキちゃんのことは嬉しかったけど、何も返せないアタシが情けなかった。気が付いたら涙が流れていて、ミキちゃんがそれにつられて、二人で泣いた。泣いたらちょっとすっきりした。アタシはミキちゃんに、これからの勤務先を伝えて、お互い頑張ろうね、って軽く励まして、また会おうね、と言って別れた。